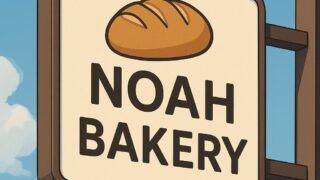びわこ虫(ユスリカ)大量発生の理由とは?滋賀の秋の風物詩と生活への影響・対策まとめ

滋賀県に暮らす人にとって、春や秋の風物詩として知られているのが「ユスリカ」の大量発生です。地元では“びわこ虫”とも呼ばれ、琵琶湖の湖岸を中心に一斉に現れる光景は驚きと不快感が入り混じったインパクトを与えます。ここでは、ユスリカ大量発生の仕組みや実際の影響、そして滋賀県民にとっての位置づけをまとめます。

ちなみにですが、今年のシーズンも本当に信じられないくらいの「びわこ虫」が僕の家のベランダにも現れ、そこで力尽き、大量のその姿を残していきました。その数きっと100や200のレベルではないでしょう。ホンマにすごいです。。
びわこ虫、ユスリカとはどんな虫?
そもそも、びわこ虫ってなんなの?というところから入っていきます。
ユスリカはハエ目に属する小さな昆虫で、蚊に似ていますが人を刺すことはありません。幼虫の時期は「赤虫」とも呼ばれ、湖底の有機物を食べて育ちます。琵琶湖には実に170種類以上のユスリカが確認(マジ?)されており、その中でも特に「オオユスリカ(春発生)」と「アカムシユスリカ(秋〜冬発生)」がよく知られています。
 ※画像はイメージです。
※画像はイメージです。発生の季節とメカニズム
ユスリカの大量発生は主に春(3〜4月)と秋〜冬(11〜12月)に集中します。これは、湖底環境や水温の変化が一斉羽化のトリガーとなるためです。条件が整うと一夜にして数百万匹規模で同時に飛び立つこともあり、湖岸一帯が霞んで見えるほどの光景になることがあります。その群れは遠くから見るとまるで煙が立ちのぼっているようにも見え、風にあおられて街中に流れ込むこともあります。近くで観察すると羽音がブーンと響き、まるで小さな嵐のような迫力を感じさせます。時には自動車のヘッドライトや信号機の周りを覆い隠すほどで、通行人が思わず足を止めて見上げることも珍しくありません。この一斉羽化は数日続くことが多く、滋賀県民にとっては季節の大イベントとして記憶に残る現象となっています。
どこで多く発生するのか
滋賀県大津市の「大津京〜膳所」エリアはユスリカ発生の“ホットスポット”として知られています。湖底にプランクトンや水草が豊富なため、ユスリカの幼虫が育ちやすい環境になっているのです。特に春先には風向きや気温の変化が重なることで一斉に羽化が始まり、夕方には湖面から雲のように立ち上がる群れが見られることもあります。夜になると街灯やコンビニの明かりに引き寄せられ、建物の壁や窓ガラス、さらには電車のホームや車の車体にまでびっしりと成虫が張り付きます。その光景は時に白い壁が黒っぽく見えるほどで、通勤通学の人々が驚きながらスマートフォンで撮影する姿も見られます。こうした状況は地元では毎年のニュースになるほどで、SNSでも「今年もびわこ虫の季節が来た!」と話題に上がり、滋賀ならではの光景として広く共有されています。

🐛 SNSで話題の『びわこ虫』投稿例集
投稿①:季節の風物詩系
琵琶湖の秋がきたなぁ〜と思う瞬間。
壁や車にびっしり「びわこ虫」!
不快だけど、毎年のおなじみの光景。
今年も無事に“群舞ステージ”開幕です😂
#滋賀あるある #びわこ虫 #秋の風物詩
投稿②:ユーモア混ぜた観察系
今日もびわこ虫が絶好調。
洗濯物にも車にも「ここが俺たちのステージ!」と言わんばかりにびっしり🤣
不便だけど、ちょっと愛着わいてくるのはなぜ。
#滋賀ライフ #ユスリカ #びわこ虫観察日記
投稿③:学び系(豆知識付き)
実は「びわこ虫」って、琵琶湖の水をきれいにしてくれてる存在。
成虫は刺さないし、人に害はなし。
ただし…大量発生した姿はやっぱりインパクト強すぎ😂
#滋賀あるある #びわこ虫豆知識 #ユスリカ
人への影響
ユスリカは人を刺したり、病気を媒介することはありません。しかし、大量発生すると光に集まる習性から建物の壁や窓、車などにびっしりと付着し、生活上の不快感を与えます。夜には明かりを求めてマンションの廊下や商店街の照明にまで群がり、扉を開けた瞬間に室内へ侵入してしまうこともあります。朝になると死骸が道路やベランダに散らばり、掃除が大変になることも珍しくありません。積もった死骸が雨と混ざると滑りやすくなり、自転車や歩行者が困るといった声も聞かれます。また、エアコンの室外機や換気扇に入り込んで詰まりを起こすケースもあり、住民にとっては思わぬトラブルの原因となります。

そのため「害虫」扱いされがちですが、実際には魚の餌になるなど湖の生態系には欠かせない存在でもあります。ユスリカの幼虫は水質浄化にも一役買っており、数が多すぎれば迷惑でも、少なすぎれば生態系に悪影響を及ぼすという、複雑な位置づけを持つ存在なのです。
びわこ虫=春の風物詩
滋賀県民にとってユスリカは「またこの季節が来たか」と感じさせる存在です。花粉や黄砂と同じように季節の到来を知らせる合図でもあり、ニュースやSNSで「びわこ虫が出てきた!」という声が飛び交うのも毎年の恒例です。夕暮れの湖岸で自転車を走らせていると、口や目に飛び込んできて「うわっ」と声を上げることもあれば、帰宅時に玄関の灯りに群がる虫の影を見て季節の変化を実感することもあります。学校帰りの子どもたちが「今日めっちゃ多かった!」と話題にするなど、地域のちょっとした会話のネタにもなります。嫌われ者でありながらも、どこか“滋賀らしさ”を感じさせる自然現象として受け止められ、春や秋の訪れを告げる一種の風物詩として定着しているのです。
びわこ虫以外で、琵琶湖周辺に大量発生する虫たち
びわこ虫(ユスリカ)は琵琶湖の代表的な虫として知られていますが、実は湖岸ではそれ以外にも季節ごとにさまざまな虫が大量発生します。ここでは、観光や日常生活にも影響する主な虫と、その発生時期をまとめました。
主な虫と発生時期カレンダー
| 虫の種類 | 主な発生時期 | 発生のピーク | 主な場所 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|
| カゲロウ | 5月〜9月 | 6月頃 | 湖岸・川沿い・明かりのある場所 | 夜に一斉羽化し、街灯に群がる。短命で翌朝には地面に積もるほど。 |
| トビケラ | 4月〜7月 | 5〜6月 | 河口・湿地・水辺 | 幼虫期を水中で過ごし、羽化すると光に集まる。水質が良い証でもある。 |
| 蚊(カ) | 6月〜9月 | 7〜8月 | 湖岸・ヨシ原・公園 | 夕方以降に活動。風の弱い日や湿地では特に多い。 |
| 羽アリ | 6月〜8月 | 梅雨明け〜真夏 | 湖岸住宅地・公園 | 結婚飛行と呼ばれる一斉飛行。短時間で収束するが、光に集まりやすい。 |
| ガ(蛾)類 | 5月〜10月 | 7〜9月 | 森林周辺・宿泊施設・街灯 | 夜間照明に集まりやすく、種類が豊富。年によって発生量に差がある。 |
観光・生活への影響
- 湖岸ドライブやサイクリング時には、特に夜間走行中にフロントガラスやヘルメット、衣服に虫が多く付着しやすくなります。車のライトに引き寄せられるため、一部のエリアでは一面が虫で覆われることもあるほどです。

- 湖畔のカフェやホテル、レストランなどの明かりには、カゲロウやトビケラ、びわこ虫などが一斉に集まることがあります。夕食時や夜の散歩の際には、照明の周囲に小さな虫の群れが見られ、外の席では少し気をつけたいポイントです。
- 春から秋にかけて開催される花火大会や音楽イベント、湖岸のライトアップなどでは、夜の明かりに反応して虫が増える傾向があります。特に風が穏やかな夜は、照明付近で舞う虫が多く、写真撮影時に映り込むこともあります。
快適に過ごすための対策
- 外出は日中メインに:夕方〜夜は虫の活動が最も活発になる時間帯です。日中のうちに屋外での散策や観光を済ませておくと、より快適に過ごせます。特に湖岸や公園などは、夕方になると一気に虫の数が増える傾向があるため、日差し対策をしつつ昼の時間を有効に活用しましょう。
- 虫よけスプレーの活用:蚊・トビケラ対策には欠かせません。肌だけでなく、服や帽子にも軽く吹きかけておくと効果的です。最近では天然成分を使った子ども向け製品や、香りの少ないタイプも増えているため、目的に合わせて選びましょう。
- 照明を工夫:屋外での食事や夜間の作業では、LEDや暖色系ライトを使用することで虫の寄りを大幅に軽減できます。光量の強い白色照明は虫を引き寄せやすいため、必要に応じて明るさを調整したり、ランタンにカバーを付けるのも有効です。
- 宿泊時の注意:ホテルや旅館では、網戸の閉め忘れやベランダの照明点灯によって虫が入り込みやすくなります。就寝前に窓周りを確認し、屋外ライトをこまめに消すことで快適さを保てます。また、宿泊施設によっては虫対策用の電撃ラケットやリキッド型蚊取りを備えている場合もあるので、必要に応じてフロントに相談しましょう。
- 車のケア:夜間走行後は、フロントガラスやライト部分に虫が多く付着します。放置すると取れにくくなるため、帰宅後や翌朝のうちに洗車するときれいに落とせます。虫取り専用クリーナーやマイクロファイバータオルを使えば、塗装を傷つけずに清掃可能です。
虫もまた、琵琶湖の豊かさの象徴
びわこ虫をはじめ、カゲロウやトビケラなどの発生は、琵琶湖の水質が良好であり、湖が今も豊かな自然環境を維持していることの証です。これらの虫たちは、決して迷惑な存在だけではなく、湖の生態系にとって大切な役割を果たしています。例えばユスリカの幼虫は魚類の餌となり、水中の有機物分解にも寄与しています。つまり、虫の多さは自然が循環しているサインなのです。
 多少の不便を感じる場面もありますが、それもまた琵琶湖という大きな自然の中で生きる一部といえます。夕暮れ時に舞うカゲロウの群れや、夏の湖岸で聞こえる虫の羽音は、静かで穏やかな時間を彩る季節の風物詩でもあります。琵琶湖を訪れる際は、虫よけ対策をしながら、時間帯や気候に合わせて散策するとより快適に楽しめます。虫たちの存在を少しだけ理解し、自然の営みの一部として受け入れることで、四季折々の琵琶湖の表情をより深く感じられるでしょう。
多少の不便を感じる場面もありますが、それもまた琵琶湖という大きな自然の中で生きる一部といえます。夕暮れ時に舞うカゲロウの群れや、夏の湖岸で聞こえる虫の羽音は、静かで穏やかな時間を彩る季節の風物詩でもあります。琵琶湖を訪れる際は、虫よけ対策をしながら、時間帯や気候に合わせて散策するとより快適に楽しめます。虫たちの存在を少しだけ理解し、自然の営みの一部として受け入れることで、四季折々の琵琶湖の表情をより深く感じられるでしょう。
まとめ
琵琶湖のユスリカ大量発生は、僕たちの生活にとって確かに「ちょっと迷惑」な現象です。洗濯物に付いたり、窓や車にびっしり張り付いたりすると「またこの季節がきたか」とため息が出ることもあるでしょう。ちなみに、洗濯物を取り込む時、Tシャツなんかにびわこ虫がひっついたまま部屋の中に入れてしまい、部屋の壁にも数匹いる!なんてことも。
けれども一方で、びわこ虫の存在は湖の豊かさや自然の循環を映し出すサインでもあります。ユスリカの幼虫は湖底の有機物を食べて水をきれいにし、魚や水鳥のエサとなり、生態系を支えています。その結果として短命な成虫が一斉に羽化し、私たちの目に「大量発生」として映っているのです。つまり、びわこ虫は“滋賀の自然が生きている証”。その姿は、不快でありながらもどこか誇らしく、琵琶湖という母なる湖と人々の暮らしが密接につながっていることを教えてくれます。
今年もまた「びわこ虫に悩まされる季節」が巡ってきます。しかし、それを単なる迷惑として片づけるのではなく、湖と共に生きる滋賀らしい暮らしの象徴として感じてみようと思います。 びわこ虫の羽音の向こうには、僕たちの生活を支える、豊かな自然のリズムが確かに息づいているのでは?なんて思います。
よくある質問(Q&A)
Q1. びわこ虫(ユスリカ)は刺すの?害はある?
A. ご安心ください。ユスリカの成虫は口が退化しており、人を刺したり吸血したりすることはありません。見た目は蚊に似ていますが、人体への直接的な害はありません。
Q2. どうして琵琶湖では大量発生するの?
A. ユスリカの幼虫は湖底で有機物を食べて育ちます。琵琶湖は栄養が豊富なため、羽化の時期になると一斉に成虫が飛び立ち「大量発生」として目に映るのです。これは湖の豊かさを示す自然現象でもあります。
Q3. びわこ虫が大量に発生する時期はいつ?
A. 主に春と秋、特に秋は発生のピークとなります。夕暮れどきや風の少ない日は、街灯や建物の壁に群がる姿がよく見られます。
Q4. 生活への影響を減らす方法は?
A. 網戸や窓をしっかり閉める、夜は室内の照明をカーテンで遮る、洗濯物は屋外で干さないなどが基本的な対策です。自治体や専門業者による駆除も行われていますが、自然現象のため完全に防ぐことは難しいとされています。
Q5. 観光客でも注意したほうがいい?
A. 人への害はないので過度に心配する必要はありません。ただ、車や衣服に付着することがあるため「びわこ虫の季節なんだな」と受け止めていただければOK。むしろ滋賀らしい風物詩として楽しむ人もいます。